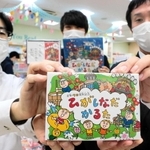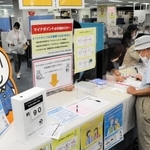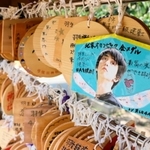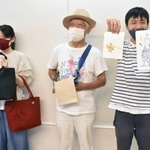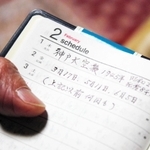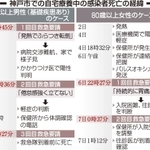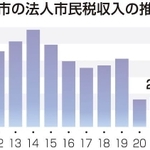神戸市東灘区は市内でも外国人人口が多く、20年に6千人を超えた。日本語に不安を抱える児童生徒も多く、新型コロナウイルス禍はその課題を浮き彫りにしたという。本庄地域福祉センター(同区本庄町2)を拠点に外国人の子どもたちの学習支援に取り組み、今年5月で設立20周年を迎えたボランティア団体「こうべ子どもにこにこ会」を取材した。(井上太郎)
■個別指導
6月下旬の夕方。放課後でにぎわう児童館の下階では、会議室に並んだ長机に10人ほどの子どもが散り散りに座り、学習に集中していた。
未就学児から中学生が通い、ルーツも南米や中国、東南アジアなどさまざまだ。漢字ドリルに鉛筆を走らせる音。教科書の詩を朗読する声。「次はこっちをやってみようか」。それぞれの隣に座った大人が促し、アドバイスを送る。
日本語の習熟度が異なるため、原則1人ずつに「担任」が付き個別に指導している。元教師や地元の大学生ら35人がボランティアに登録している。
1回2時間の週2回で、2千円の月謝を光熱費などに充てて運営する。日本語に慣れれば算数や英語も教え、「日本語も教科支援もシームレス(継ぎ目なく)に対応している」と、同会代表の北村広美さん(57)。夏休みは宿題教室、年末はパーティーを開いて親睦を深める。
■ボーダーレス
阪神・淡路大震災後に深江で開講した日本語教室から子どもの指導に特化して独立し、2002年5月に立ち上げた。日本語の理解が不十分で学校の授業についていけない子どもの精神的ケアに努め、08年には東京の財団法人に表彰もされた。
神戸市内でも外国人人口が多く、20年に6362人を数えた東灘区。ボランティアによる日本語支援は盛んで、住吉、岡本、御影など各地に教室がある。にこにこ会に通うのは主に本庄、東灘小学校区の子どもら。北村さんによると、当初は南米にルーツを持つ外国人が多かったが、最近は中国、フィリピン、ネパール、パキスタンなど「特定の民族コミュニティーがなくボーダーレス」な傾向にある。
■息の長い支援
文部科学省の調査では、日本語指導が必要な児童生徒は日本国籍、外国籍合わせて21年度に約5万8千人おり、約3万4千人だった10年度から1・7倍に増えている。こうした児童生徒の高校や大学への進学率は平均を下回り、非正規の就職率も39%で平均の12倍に上る。
一方、いずれの指標も徐々に改善傾向にある。北村さんは「学校や教育委員会から適切な団体につながるケースは、ここ数年で増えてきた」と感じている。
にこにこ会を巣立った後も、同じ東灘区の深江南町を拠点にする外国人支援施設「多文化共生センターひょうご」を窓口に、進学や就職の相談に乗り、息の長い支援を心掛けているという。
■コロナで再認識
新型コロナの感染拡大を受け、20年春は臨時休校が相次いだ。自宅学習ではインターネット環境が整っていなかったり、保護者が日本語に不慣れなため宿題を見てもらえなかったりして学習機会を十分に持てない子どもがいた。
にこにこ会では最初の緊急事態宣言下こそ教室を自粛したが、不利な境遇の子どもたちのためにも、宣言解除後は早めに再開に踏み切った。北村さんは「成績もそうだが、居場所づくりという意味でも大切な役割があることを再認識した」と気を引き締めている。
本庄地域福祉センターでの活動は毎週木曜、土曜の午後4時~6時。ボランティアに参加したい人は同会(TEL078・453・7440)まで。
→「東灘区のページ」(https://www.kobe-np.co.jp/news/higashinada/)
-
神戸東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
神戸未来を変える東灘話題

-
神戸未来を変える東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸震災28年東灘話題

-
震災28年神戸東灘話題

-
神戸震災28年U28震災後世代東灘話題

-
神戸震災28年東灘話題

-
スポーツ震災28年東灘話題ラグビー

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題ウクライナ侵攻

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
文化神戸東灘話題

-
教育神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸教育東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
東灘話題神戸

-
神戸東灘話題

-
神戸スポーツ東灘話題

-
神戸東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題震災28年

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
明石東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
文化神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸新型コロナワクチン東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸文化東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題東灘・気になるあの店

-
東灘話題

-
東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸教育東灘話題

-
東灘話題東灘・気になるあの店

-
東灘話題

-
東灘話題

-
神戸新型コロナワクチン東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
神戸東灘話題

-
新型コロナ神戸東灘話題

-
東灘話題

-
神戸東灘話題

-
文化神戸東灘話題

-
神戸新型コロナ東灘話題

-
東灘話題

-
東灘話題

-
神戸東灘話題

-
東灘話題

-
新型コロナ神戸東灘話題