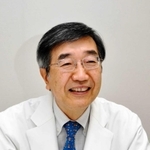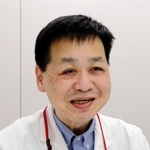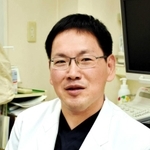胃や十二指腸の病気の多くに、ピロリ菌が関わっています。すみかは胃の中。本来、胃酸が出て菌の生きられない場所ですが、ピロリ菌は周りを中和します。「ウレアーゼ」という酵素でアルカリ性の環境を生み出せるからです。毒素をまき散らし、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などを引き起こします。最悪の場合は胃がんに至ります。
感染経路は、他人の唾液や井戸水と考えられています。高齢者の感染率が高いのはこのためです。つまり、母が子に口移しで食べさせるのが普通で、上下水道が普及していなかった時代に生まれたことが原因とされています。
逆に言うと、衛生環境が整った現代では、感染率は著しく低下しており、あまり神経質になることはないでしょう。それでも、人は人と接しながら生きている以上、ピロリ菌の感染確率をゼロにすることはできません。だからこそ、早期発見と除菌が大事になってくるのです。
おなかの痛みやむかつき、胃もたれなどを頻繁に感じるようなら、ピロリ菌感染を疑い、医療機関にかかり、内視鏡検査を受けてピロリ菌を調べるべきでしょう。
内視鏡で胃の組織を採る検査は保険が適用され、自己負担は5千~1万円程度です。顕微鏡で観察する「鏡検法」や、ピロリ菌が増えるか試す「培養法」がありますが、特定の胃薬を飲んでいないなどの条件がそろっていれば、ウレアーゼを特定する試薬を使い、30分ほどで結果がわかる「迅速ウレアーゼ試験」がよいかもしれません。また、内視鏡を使わない検査で最も精度が高いのは「尿素呼気試験」といい、尿素を含む検査薬を飲み、吐く息が重くなったかを測定します。
感染がわかれば、除菌をします。胃酸の分泌を抑える薬と、2種類の抗菌薬を、朝夕2回、7日間飲みます。除菌ができていなければ、抗菌薬のうち1種類を変更し、さらに7日間飲み続けます。
2度目の除菌までは保険が使えます。2度除菌しても数%の人にピロリ菌が残ります。保険外でさらに除菌を続けるか、定期的な検診で異常を見逃さないよう努めるか、主治医と相談してください。
除菌した人の胃がん発症率は約3分の1に下がる、と報告されています。ただ、感染歴があれば、胃が攻撃されて荒れているため、がんになりやすい体質になっています。塩分やたばこ、アルコールを控え、ストレスをためすぎない生活を心掛けてください。(聞き手・佐藤健介、協力・兵庫県予防医学協会)
【しらさか・だいすけ】1969年、加古川市生まれ。広島大医学部卒。神戸大病院を経て、2007年から現職。食道から胃、十二指腸までを対象とする上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)に精通する。ピロリ菌感染症認定医。
白坂さんが勧める三つの作法
一、ピロリ菌をチェックし、陽性なら除菌する
一、内視鏡などの検診を定期的に受ける
一、たばこは吸わず、飲酒と塩分摂取は控えめに
ピロリ菌
学名は「ヘリコバクター・ピロリ」。胃や十二指腸の潰瘍を起こし、胃がんの原因とされる。らせん状の細菌で、大きさは千分の4ミリほど。酵素でアンモニアを合成して胃酸を中和するため、強酸性で滅菌状態の胃の中で生息できる。