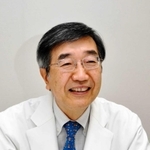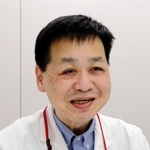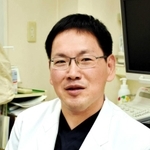同時期に多くの薬を服用する「ポリファーマシー」(多剤併用)が問題になっています。年齢とともに体が不調になる機会は増え、高齢者ほど服用する薬が多くなる傾向があります。70歳代になると、平均8種類の薬を服用しているというデータもあります。
絶対に安全で、副作用がない薬はありません。薬の服用数が増えるほど、薬の有害事象が起きる確率は高まります。薬を10種類以上服用する20%以上の人に有害事象があったとする国内の報告があります。高齢の入院患者の6~15%に薬物の有害作用があり、高齢になるほどその割合が増えたという例もあります。海外では、薬による有害事象が2種類服用で13%、4種類で38%、7種類以上では82%に上ったというデータもあります。
さらに米国では、高齢者の救急入院患者の1・5%が薬の副作用が原因で、その約半数は80歳以上だったと報告されています。その3分の2の人の原因になった薬剤として、血液をさらさらにするワルファリン、抗血小板薬、血糖値を下げるインスリン、経口血糖降下剤が関係していたといいます。これらの薬は多くの人によく処方される大切なものです。特別な薬だけが問題を起こすわけではないことに気をつける必要があります。
服用する薬の数が増えれば、飲み忘れや飲み間違いも増えますし、薬剤の相互作用も増えます。
ただし、薬の数が多いことが一概に悪いわけではありません。大切なことは、自分がどんな薬を飲んでいるのかを知っておくこと、不安や疑問があればかかりつけ医や薬剤師に相談することです。自分の判断で薬をやめたり、飲む量を変えたりしてはいけません。あちこちの医療機関を紹介状なしに受診することは、薬の情報が共有されずに、薬に伴う有害事象のリスクを高めることになります。自分に合った良いかかりつけ医を持つことが大切です。
「お薬手帳」も大切です。私の外来にも、手帳を持たない方が多く受診されます。服用中の薬が分からない場合、診断が混乱したり、新たな薬を処方できなかったりします。体調不良は薬のせいかもしれません。サプリメントや健康食品も、薬との相互作用があるので、何をどれだけ飲んでいるか伝えることも忘れないでください。(聞き手・山路 進、協力・兵庫県予防医学協会)
【にしおか・ひろあき】1967年、京都府生まれ。京都大医学部卒。名古屋記念病院総合内科部長などを経て、2011年に中央市民病院へ。日本内科学会総合内科専門医・指導医。日本老年医学会専門医・指導医。奈良県生駒市在住。
西岡さんが勧める三つの作法
一、医師にかかる際は必ずお薬手帳を持って行く
一、自分の判断で薬を服用したり、やめたりしない
一、サプリメントや健康食品の使用状況も医師に伝える
上医は薬を知る
江戸時代の本草学者貝原益軒が著書「養生訓」に記した。「上医は病を知り、脈を知り、薬を知る」「下医は三知の力なし。みだりに薬を投じて、人をあやまること多し」。西岡さんは「昔から薬の飲み方が大切なことは変わらない」と言う。