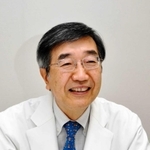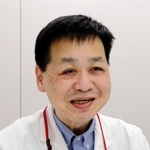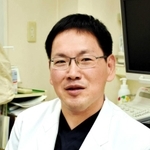「人の老化は血管の老化から始まる」とも言われるように、健康長寿にとって血管を若々しく保つことは大切です。つまり、動脈硬化を起こさないようにする、ということです。
やっかいなのが、動脈硬化そのものには自覚症状がない点です。検査をすれば分かるので、定期的に受けることをお勧めします。放っておくと血管が狭くなって血流が悪くなり、足がしびれたり、胸が苦しくなったり、めまいがしたりします。さらに悪化すると、心筋梗塞や脳梗塞につながってしまいます。
動脈硬化は血圧が高くなったり、たばこを吸ったりすることで、血管の「内皮細胞」に傷が入ることから始まります。傷を治そうとして炎症が起きると、血管がさびついたような状態になり、徐々に“ごみ”が付き始める。その代表例がコレステロールです。最初のうちは「マクロファージ」という細胞が食べて処理してくれますが、処理しきれなくなると古いコレステロールが血管の壁にたまり、狭くなっていきます。
医療の進歩によって、心筋梗塞や脳梗塞になっても命は助かるケースが増えていますが、入退院を繰り返したり、日常生活に復帰できなかったりする場合も増えています。介護などを必要としない健康寿命と平均寿命の間には10年近いギャップがありますが、そこには動脈硬化も大きく影響していると言えます。
予防に欠かせないのは、やはり生活習慣の見直しです。食事なら、欧米風よりも魚と野菜を中心とする和食がいい。脂肪分や塩分の取り過ぎには注意が必要ですが、青魚に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)といった脂肪は動脈硬化防止に効果的とされます。食物繊維もしっかりと摂取してください。
適度な運動も重要です。散歩や自転車などで1日30分程度の運動をするのが理想的ですが、ポイントは日常生活の中で、無理なく体を動かすこと。例えば家にいるときに、立ったり座ったりするのも運動の一つです。
たばこは「もってのほか」ですが、実は精神的なストレスもよくありません。血圧が上がったり脈が速くなったりすると、血管に負荷がかかって動脈硬化につながります。できるだけ楽観的に物事を考え、嫌なことがあってもくよくよしない。毎日楽しく、笑って過ごしましょう。(聞き手・田中陽一、協力・兵庫県予防医学協会)
【ひらた・けんいち】1958年、三田市生まれ。神戸大大学院医学研究科修了。専門は循環器内科学。2007年に同研究科教授、11年から神大医学部付属病院副病院長。日本循環器学会、日本動脈硬化学会などの理事も務める。
平田さんが勧める三つの作法
一、食事はバランスよく。偏りや太りすぎには注意を
一、日常生活の中で適度に体を動かすよう心掛ける
一、たばこは禁物。ストレスも避けよう
動脈硬化の検査
一般的な健康診断では検査項目に入っていないことも多く、気になる場合は病院で検査を。頸(けい)動脈をエコーで見たり、専用機器で四肢の脈波を測定したり、上腕を圧迫した後に動脈の拡張を調べたりする手法がある。