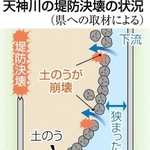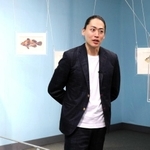兵庫県尼崎市東七松町2にマンモス学舎があると思ったら、別々の中学校が隣り合わせに建っていた。市立の日新中と中央中だ。2校を隔てるのは緑色のフェンスのみ。全国でも珍しい2校の「隣設」には、1950年代以降の市内の急激な人口増加が背景にあった。(村上貴浩)
北側に日新中、南側に中央中の敷地が広がる。正門は共に西側にあり、その間隔は歩いて数十歩しかない。毎朝、異なる制服の生徒たちが一緒に現れてそれぞれの正門に吸い込まれていく。
日新中の敷地に入らせてもらうと、中央中との境界にはフェンスが張られ、両校にまたがる建物もある。プレートには「配膳室」の文字。今年から市内の中学校で給食が始まり、食材を搬入する場所だという。
「もともとは両校が食堂として使っていた場所でした。扉の先は中央中。給食は通路の都合上、中央中の敷地からしか運び込めません」と松村高志教頭。
東に進むと、フェンスの一角に両校を行き来できる門があった。ごみ収集時などに使われているらしい。
「通称、ワープゾーン。中央中の正門に給食のトラックが来ると、中に止めている車は出られなくなるので、ここを使って日新側から出たりします」と中央中の小林誠一郎教頭が話す。生徒は普段通らないが、2校の体育館がまとめて部活動の大会会場になって生徒に開放することもある。
校舎の窓から顔を出すと、互いの生徒と会話ができるほどに近い。「昔は窓からケンカをふっかけたりしていたみたいですけど、今は仲良く手を振り合ったりしてますよ」
◇
なぜ二つの公立中学校が真隣に建っているのか。
尼崎市歴史博物館の辻川敦さんに聞くと、1950年代以降、市内では工業の発展に伴って人口が急増。子どもが増えて学校の新設が求められたが、用地が見つからない。
唯一あったのが、中央中(当時・昭和中)の真隣で食品会社「キッコーマン」が所有していた空き地だった。急ピッチで工事を進めて1959年、日新中が設立され、近隣中学校の校区を分割して引き受ける形になったという。
2校の正門が並ぶ境界付近に立って地面を見ると「←」のマークが刻まれていた。松村教頭は「これが正確な境界線です。フェンスそのものはぎりぎり日新中の敷地内ですね」と笑った。
◇
■飛び地のような校区編成 日新中校舎、中央中の校区内
隣り合う2校の特殊な関係は、その校区にも表れている。日新中は開校時に中央中(当時・昭和中)と近くの立花中の校区を分割して引き取ったため、飛び地のようないびつな校区編成になっている。
地図を見ると驚くことに、日新中の校舎は中央中の校区内に存在している。そのため、日新中の正門前に住む生徒は目前の校舎を通り過ぎて中央中に通っている。
また、尼崎市教育委員会によると、過去には中央中の校区内にある難波の梅小学校(尼崎市西難波町6)の児童が2校に別れて進学していたことも。「校区は通学路の安全性や、地域からの要望などをもとに編成している」といい、直近では2020年度の入学生から校区の再編が実施され、中央中に集約された。
尼崎市の武庫小と武庫の里小、西宮市の段上小と段上西小など2校が接近しているケースは全国にあるが、「隣接」は異例。ただ、昭和から平成、令和に時代が変わって少子高齢化が加速し、尼崎市内でも小中学校の統廃合が続く。
19年度に生徒数が467人だった日新中は22年度に392人と減少しており、一方で中央中は600人から666人に増加している。将来はフェンスがなくなる日が来るかもしれない。
(村上貴浩)

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神