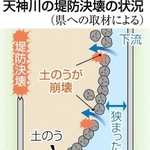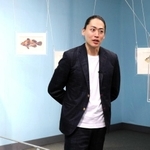兵庫県尼崎市の阪神尼崎駅前にある中央公園を歩いていると、何やら熱い視線…。木陰から、いかめしい顔でハンマーを振りかざす銅像がこちらをにらんでくる。さらに、近くには芝生広場の中央にクスノキの一本木がそびえる。実は、どちらも間もなく設置から半世紀。この二つは当時、尼崎が工業で栄えたことをたたえつつ、公害問題の解決を願うという「工都」の光と闇を象徴しているのだ。(村上貴浩)
50年前の1972(昭和47)年の尼崎市といえば、人口が約55万人とピークに達し、第1回の市民祭りが開かれて街は活気にあふれた。一方で南部の空には黒煙やスモッグが立ち込め、工業廃水でごみためのようになった川もあった。公害対策審議会が設置されるなど、市民運動も盛んになった時期でもあった。
市の玄関口に二つのオブジェが生まれた経緯を調べてみた。
■工都尼崎青年の像
像は左手にペンチのような道具を持ち、右手のハンマーを打ち下ろそうとしている。片膝立ちで踏ん張る足元には炎が噴き上がっている。
そう、まさに製鉄作業員の姿だ。当時の資料によると、工業の神様と尼崎の労働者を表現したといい、火打ちして作っているのは、その名も「繁栄の鍵」。像の正式名称は「工都尼崎青年の像」だが、市民の間では「鉄鋼戦士の像」の呼び名でも親しまれている。
72年11月、尼崎ライオンズクラブが設立15周年に設置した。台座を合わせて高さは約4メートルで、総工費は当時の金額で300万円かかったらしい。
作者は地元の彫刻家、胡本蟹平さん。台座には「躍進する工都 尼崎の姿」との前書きで碑文がある。
当時の資料には「工都にふさわしいシンボルを」と設置理由を記しつつ「尼崎市には文化的な面が非常に少ない」とあり、市民が美術品に触れられる空間をつくる狙いもあったようだ。
一方で、こんな言葉も。「人それぞれのお考えもある事とは存じます」。工都としての発展を顕彰するも、深刻化する公害問題を前に手放しでは喜べないという当時の事情がにじむ。
■四国銀行の石碑
そんな世相の中、銅像と同時期の72年10月に植樹されたのがクスノキだ。木の下には高さ約2メートルの石碑を置いて「尼崎に緑と青空を」と刻む。
設置したのは、高知県に本店を構える「四国銀行」。尼崎支店の開業を記念して「高知のように、きれいな空気の街になってほしい」との願いを込め、石碑にも高知県産の「吉野川青石」を使ったという。
四国銀行は関西への進出を進める中、支店開業時には地域で完成パーティーを開くのが慣例だった。しかし、尼崎支店はオイルショックなどの影響でかなわず、石碑とクスノキの寄贈に変更。当初は2本を植えたが、1本は枯れてしまったという。
■50年を節目に
半世紀が迫り、「工都」を支えた尼崎の鉄鋼業は企業の再編などで縮小しつつ、機械工業の台頭もあって、製造業は今も関西経済を支える。一方で公害問題は88(昭和63)年に公害指定地域が解除され、国道43号排ガス訴訟やアスベスト問題を経て、街は再生しつつある。
尼崎ライオンズクラブの木和田喜博会長(79)は「街はどんどんと変わっていったが、尼崎の歴史を示す私たちの像が残っていることは誇らしい」と胸をはった。
四国銀行尼崎支店の梶原政幸支店長(47)は設置50年の節目に石碑とクスノキのイラスト付きの置き時計を得意先に配る予定という。
「人情にあふれる尼崎の街で50年間、(銀行業を)続けさせていただき、感謝しかない。石碑はその歴史の一つです」

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神