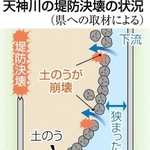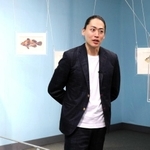最先端のロボット技術を競う19歳以下の「ロボカップジュニア2021」で、兵庫県尼崎市立尼崎双星高校(同市口田中2)の情報技術部の3人チーム「双救(そうきゅう)」がレスキュー部門で全国優勝した。今年はコロナ禍で大会全てが初のオンライン開催となり、全国の小中学生や大学生の計150チームが参加。双救は強豪・灘高校のチームも破り、6月にフランスで開かれる世界大会に日本代表として出場する予定だ。(村上貴浩)
情報技術部が活動する教室に入ると、英数字や記号が大量に打ち込まれたパソコン画面が並び、教室の中央でサッカーボールサイズのロボットが動き回っている。生徒たちはプログラムやロボット部品の改善点を熱っぽく専門用語で議論するが、部員9人の大半は高校入学までパソコンすら触ったこともなかった。
「ロボカップ」は1992年に日本で発足し、ロボットチームが対戦する「サッカー」や、災害時の救助活動を想定した「レスキュー」などの種目がある。「2050年までに人間のサッカー世界優勝チームに勝てるロボットチームを作る」という目標を掲げ、97年には愛知県で初の世界大会があり、今は約40カ国で開かれている。
今年はオンライン開催となり、双救の3人は学校の教室にパソコンを並べて出場。レスキュー部門は、仮想空間のマップに障害物とターゲットが配置され、画面上のロボットがターゲットを集め、指定された場所にどれだけ運べるかを点数で競う。ロボットは操作するのではなく、自動で動くため、どれだけ綿密にプログラミングできるかが勝負を分ける。
午前9時、メンバーは大会本部から課題のマップを示され、一斉にキーボードをたたき始めた。ロボットが障害物を素早く、正確に認識するよう、多種多様なセンサー機能を設定しないといけない。しかし、いざロボットを作動させようとしても、動かない-。「もう終わった…」。一度は諦めかけたが猛スピードで作業を見直し、提出時間になんとか間に合わせた。
いざ決戦。6チームが総当たり形式でぶつかる。
ヤマ場は2戦目に迎えた。相手チームは、世界大会で優勝経験もある灘高校の「Ninja」(ニンジャ)。双救はロボットの動作力に不安を残しつつ、画面を祈るように見守った。すると、どんどん点差が開き、結果は快勝。優勝が決まった瞬間、部員全員が画面の前で抱き合っていた。
「ロボカップの世界は本当に奥が深い」と部長の古川心音(しおん)さん(17)がしみじみと語る。各部門の優勝者には日本代表として世界大会の出場権が与えられ、次は大舞台で頂点に立つことを目標に言った。
「日本の公立高校の、意地をみせてきたい」

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神