東京大学未来ビジョン研究センター 江守正多教授
豪雨災害、温暖化で被害拡大
国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、科学的な知見から温暖化への強い危機感を示す。私たちが置かれている状況について、IPCC報告書の主執筆者の一人で、東京大学未来ビジョン研究センターの江守正多教授(気候科学)に聞いた。(聞き手・石沢菜々子)
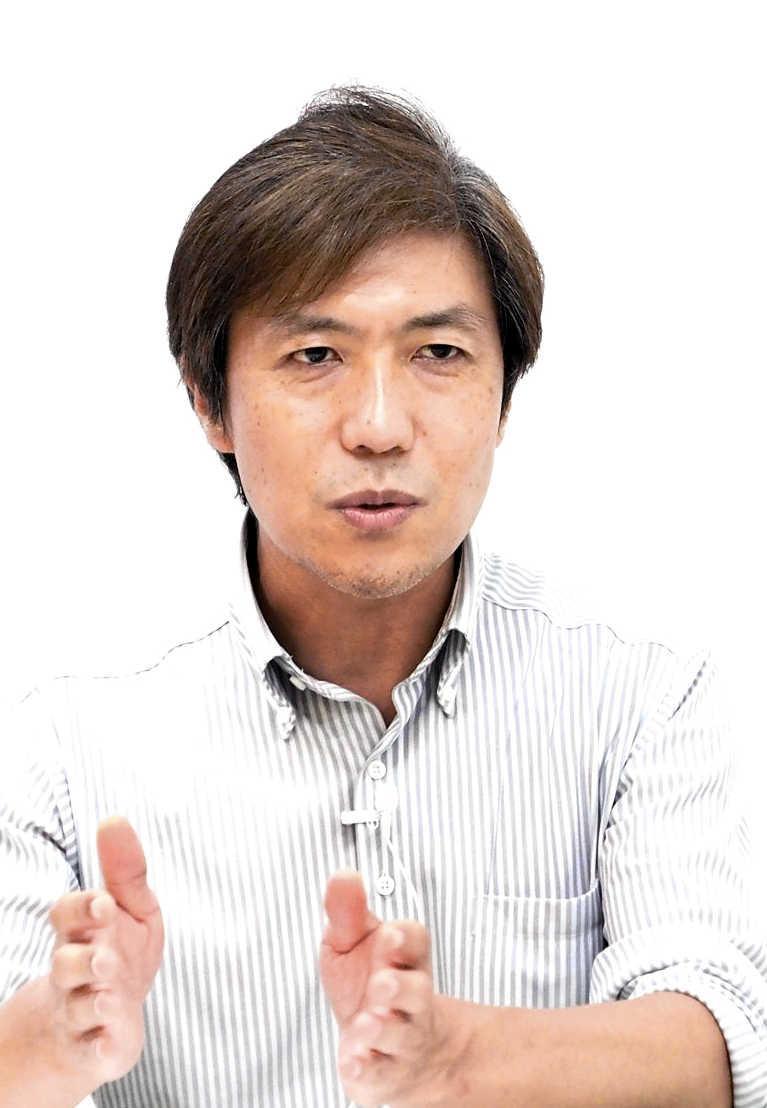
江守正多氏(提供写真)
-最新の報告書のポイントは。
「世界の平均気温は産業革命前から1・1度上がっており、ほぼ人間のせいです。世界が目指す1・5度で止めるには、二酸化炭素(CO2)排出を今世紀半ばに実質ゼロ、その先はマイナスにしないといけませんが、現状は全く軌道に乗っていません。2030年の各国の自主的な排出削減目標が達成されても、今世紀末に2・5度前後上がるペースです」
-日本でも被害が出ている。
「例えば、18年の猛暑は人間活動による温暖化がなければ起き得なかった暑さだった、といったことが最近の研究で分かっています。同年の西日本豪雨や19年の台風19号も、温暖化がなければそこまでの被害にはならなかった。暑い年や大雨はたまにありますが、温暖化で追加的な被害を受けているという認識です」
「リスクの一つは生態系への悪影響です。温度変化で生息地を移動しなくてはならない生物もいます。農業や漁業、雪不足による観光地へのダメージなど、経済活動への悪影響も出ています」
-社会システムを持続可能なものに変えていくには。
「例えば建築物省エネ法が改正され、25年度からは新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。東京都では新築住宅へのパネル設置が義務化され、川崎市でもやろう、という流れがある。ある程度規制が入り、『やるのが当たり前』にならないと間に合いません。理解し、賛成する人が増えていくことが今、一番大事だと思います」
「海面上昇や干ばつで苦しむ発展途上国の人々には責任がなく、CO2を多く出す国に原因があります。将来世代は後から生まれてくるほど深刻な悪影響が出た地球で生きていかなくてはいけない。前の世代が原因をつくり、どのくらい対策をするかも決めているのです。こうした理不尽さに目を向けてほしい」
【えもり・せいた】1970年、神奈川県生まれ。東大大学院博士(学術)。97年より国立環境研究所勤務(現在は上級主任研究員)。22年より現職。



